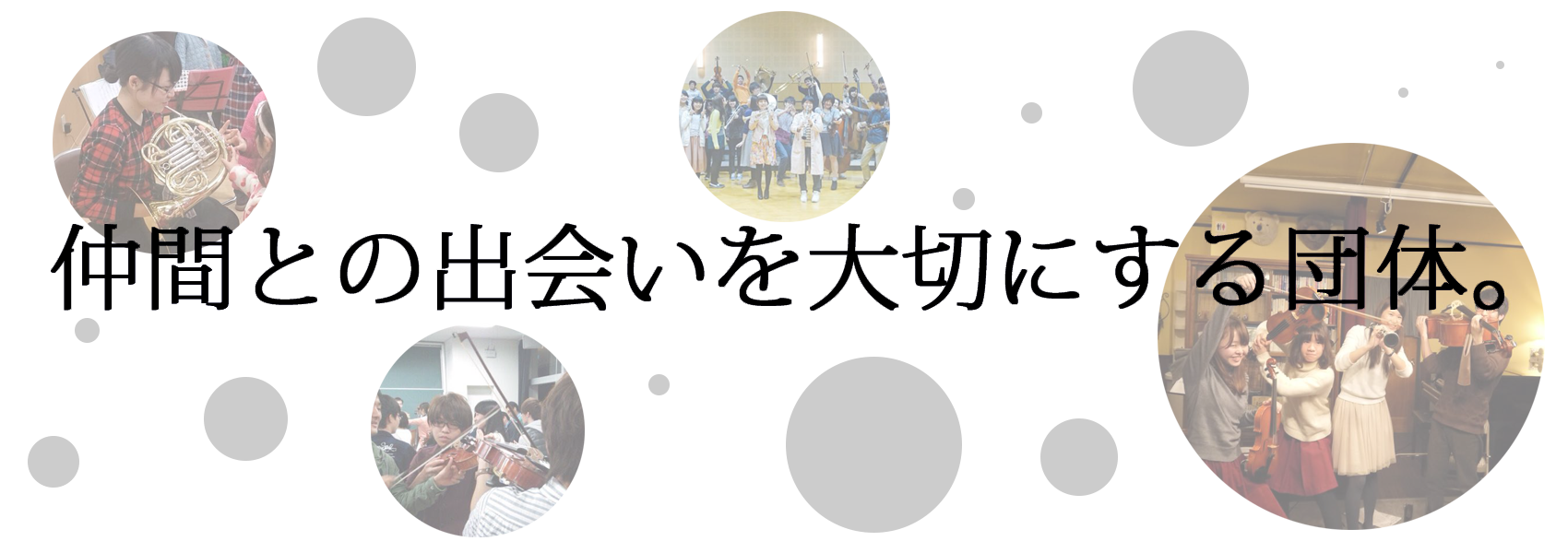
九大フィルはともに頑張る仲間のことを大切にしています。
私たちは年に2回の定期演奏会の成功を九大フィルの第一の目標に据え、
毎回練習に多くの時間を費やしています。
同じ目標に向かって努力を重ねる中で生まれる年齢や大学・学部を超えた多様な出会いは、
生涯の友人の獲得、あるいは今まで気づかなかった自分を発見する機会になるなど、
一人ひとりの部員にとって大学生活の貴重な財産になります。
そのため九大フィルは部内の人と人との関係がとても密接で、
だからこそ日々の練習を共にする仲間との出会いや交流を演奏と同様に大切にしています。

私たちの定期演奏会には毎回会場が満席に近づくほどの多くのお客様にご来場いただいています。
このように多くのお客様に来ていただけることは、
地域の皆様のご理解、ご協力があってこそのことです。
創部100年を越えた現在に至るまで一貫して寄せていただいている皆様の温かい思いに応えるため、
そしてより多くの方々に九大フィルのことを知って欲しいという思いで、
地域の幼稚園やレストランでカルテットなどの出張演奏を行っています。
私たち九大フィルは今日まで培ってきた”人”という財産をこれからも大切にし、
地域の皆様、そしてこのオーケストラに長年関わってくださったトレーナーの皆様や
OB・OGの皆様をはじめとした多くの皆様に
これからも愛される団体であり続けられるように日々精進して参ります。
幹事長挨拶
私たち九大フィルハーモニー・オーケストラ(通称:九大フィル)は、九州大学および福岡市近郊の大学に通う学生を中心に構成された、115年以上の歴史を持つオーケストラです。現在は約80名の現役部員が所属しており、年2回の定期演奏会を主軸として活動しています。
また、定期演奏会のみならず、外部の方々からのご依頼を受けて、出張演奏も行っております。幼稚園や小中学校等の教育現場をはじめ、企業の祝典行事、学会、公民館、結婚式等、多様な場で演奏の機会をいただき、幅広い音楽活動を続けています。ご興味のある方は、ぜひ「出張演奏」のページをご覧ください。
九大フィルは、九州大学客員教授である鈴木優人先生に、ミュージック・アドバイザーとして音楽指導をいただいております。鈴木先生は、バッハ・コレギウム・ジャパン(BCJ)首席指揮者、読売日本交響楽団指揮者/クリエイティヴ・パートナー、関西フィルハーモニー管弦楽団首席客演指揮者を務められるほか、鍵盤楽器奏者としても世界各地でご活躍されています。
2026年6月6日には、鈴木先生の指揮のもと、第216回定期演奏会をアクロス福岡シンフォニーホールにて開催いたします。13時開場、14時開演を予定しております。曲目は、ロッシーニ/歌劇「セビリアの理髪師」序曲、コルンゴルト/ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 作品35、チャイコフスキー/交響曲第6番 ロ短調 作品74「悲愴」です。
ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 作品35では、ソリストとしてヴァイオリニストの廣津留すみれさんをお迎えいたします。廣津留さんは、これまでにデンマーク国立フィルハーモニー管弦楽団、東京フィルハーモニー交響楽団、関西フィルハーモニー管弦楽団等と共演され、2022年にはギル・シャハム氏とThe Knightsのメンバーとして共演したアルバムがグラミー賞にノミネートされるなど、国内外で幅広くご活躍されています。
演奏活動のみならず、多方面において第一線で活動されている鈴木先生や廣津留さんと共演できる貴重な機会を大切にし、皆様の心に残る音楽をお届けできるよう、より一層研鑽を重ねてまいります。
今後とも九大フィルは、地域の方々や演奏会にお越しいただくお客様をはじめ、多くの方々に愛され、日本の音楽文化に貢献できる団体を目指していく所存です。
これから大学生になるみなさん、九大フィルの一員として、ともにすばらしい音楽をつくっていきませんか?九大フィルは楽器の経験を問わず、新入部員の入団を心から歓迎しております。
2026年1月
九大フィルハーモニー・オーケストラ 幹事長 寺﨑万優子
九大フィルの歴史
九大フィルの歩み
 榊保三郎と九大フィルハーモニー会 九大フィル(フィルハーモニー会)は、現在の九州大学医学部の前身である福岡医科大学の精神病学教室初代教授の榊保三郎によって設立されました。1909(明治42)年九大フィルの活動が始まり、九州帝国大学が発足と共に更に活動を充実させました。演奏の多くは日本初演か日本人による初めての演奏と言われています。
榊保三郎と九大フィルハーモニー会 九大フィル(フィルハーモニー会)は、現在の九州大学医学部の前身である福岡医科大学の精神病学教室初代教授の榊保三郎によって設立されました。1909(明治42)年九大フィルの活動が始まり、九州帝国大学が発足と共に更に活動を充実させました。演奏の多くは日本初演か日本人による初めての演奏と言われています。
榊と九大フィルは自らの演奏会に加えて、国内外の著名な演奏家のリサイタルも頻繁に開催し、福岡での洋楽文化の黎明を先導していきました。その頂点の一つが、1924年(大正13年)の1月26日に催した、皇太子(後の昭和天皇)の結婚を祝う「摂政宮殿下御成婚奉祝音楽会」でした。
「歓喜の歌」で有名なベートーヴェンの交響曲第九番の最終楽章を、原曲のシラーの詞ではなく文部省がこの日のために選定した「皇太子殿下御結婚奉祝歌」の歌詞に替えて演奏しました。歌詞が原曲とは異なりますが「第九」の第四楽章「歓喜の歌」を一般の日本人が初めて演奏しかつ聴いたとされています。
榊は1925(大正14)年に九大を去り、1927年(昭和2年)には九大フィルハーモニー会に代わって学友会に音楽部が誕生しました。
九大音楽部の活動

榊が去った後は、創立期から参加していた荒川文六らが中心となって引き続き安定した活動を続けていきました。しかし、昭和が進むにつれて政情不安が強まっていき、1943(昭和18)年になると学徒出陣が始まって、その年の12月の演奏会でもって戦前の活動に終止符が打たれました。
戦後の再建から今日へ
 終戦からほぼ2年を経た1947(昭和22)年6月に戦後初めての演奏を行いました。4年後の1951(昭和26)年に東京に活動の場を拡げるとともに、九大フィルやNHK福岡放送局楽団のメンバーを中心に、現在の九州交響楽団の前身である福岡交響楽団を結成しました。
終戦からほぼ2年を経た1947(昭和22)年6月に戦後初めての演奏を行いました。4年後の1951(昭和26)年に東京に活動の場を拡げるとともに、九大フィルやNHK福岡放送局楽団のメンバーを中心に、現在の九州交響楽団の前身である福岡交響楽団を結成しました。
1966(昭和41)年には、作曲家の黛敏郎が司会をしていたテレビ番組「題名のない音楽会」に出演して、全国に紹介されています。 福岡・九州の音楽文化を長く先導したことや活動の質を飛躍的に向上させたことから、創立50周年の1959(昭和34)年に西日本文化賞、1998(平成10)年には全日本大学オーケストラ大会で大賞、そして創立百周年の2009(平成21)年には福岡市民文化活動功労賞をいただきました。
2014(平成26)年に、新たな指導者として鈴木優人をミュージックアドバイザーに迎え、今日に至っています。
組織概要
 九大フィルハーモニー・オーケストラ
九大フィルハーモニー・オーケストラ
| 住所 | 〒819-0395 福岡市西区元岡744 九州大学課外活動施設Ⅱ |
| アドレス | qdaiphil@gmail.com |
| 設立 | 1909年 |
| 代表者 | 幹事長 寺﨑 万優子 |
| 幹事会 | 幹事長 寺﨑 万優子 |
インスペクター 永岡健太郎
副幹事長 大島奏穂
広報 日髙慶
渉外 池田宗弥
会計 上田慶子
庶務 槇山歩花
顧問 藤本望
ミュージックアドバイザー 鈴木優人
